19世紀後半、江戸時代の浮世絵版画が欧米で熱狂的に受け入れられ、「ジャポニスム」と呼ばれる日本美術ブームが巻き起こりました。その中心的存在となったのが、浮世絵師・葛飾北斎(1760–1849)です。
モネやゴッホといった名だたる西洋の画家たちは、異国の浮世絵、なかでも北斎の作品に強い衝撃を受け大いに魅了されました。
本記事では、北斎が世界の画家たちに与えた影響の秘密に迫り、その芸術的インパクトを読み解いていきます。
目次
葛飾北斎とは
まず、葛飾北斎とはどのような人物だったのでしょうか。
北斎は江戸後期に活躍した浮世絵師で、生涯に約3万点ともいわれる作品を手がけたとされます。風景版画集『冨嶽三十六景』に代表される壮大な構図の風景画や、絵手本『北斎漫画』に収められた生き生きとした人物・動植物のスケッチなど、その題材は多岐にわたり創意工夫に富んでいました。
特に1830年代に制作された「神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)〈冨嶽三十六景〉」は世界的に著名で、今日では「史上もっとも有名な日本美術の一つ」とも評されています。
北斎の斬新な作品群は、同時代の日本国内のみならず、後に海外の芸術家たちにも大きな刺激を与えることになったのです。
西洋に伝わった北斎とその評価
幕末から明治初期にかけて日本が開国すると、浮世絵版画などの美術品が欧米にもたらされました。
例えば、輸出陶磁器の梱包紙に使われていた浮世絵がヨーロッパ人の目に留まり、その鮮やかな色彩と画風が「それまで見たことのない美」として驚きをもって迎えられたと伝えられます。
1867年のパリ万国博覧会では日本美術が公式に紹介され、以後浮世絵は美術品として大量に海外へ渡って西洋で爆発的に広まりました。
こうした中、北斎の名前は西洋の画家や批評家の間で広重以上に広く知られる存在となります。
1880年代のフランスでは美術誌上で「我らがこれから知り愛するであろう日本の偉大なる芸術家、北斎よ。その秘訣のいくばくかを我らに明かしてほしい」と北斎への憧憬を綴る評論家も登場しました。
フィンセント・ファン・ゴッホは弟テオへの書簡で興奮気味に「北斎」や「広重」の名を幾度も言及しており、生涯で400点以上の日本版画を収集した熱烈な浮世絵愛好家でした。
また北斎の絵手本『北斎漫画』は「ホクサイ・スケッチ」の名で欧州でも親しまれ、印象派のエドゥアール・マネや象徴派のギュスターヴ・モローによって幾度も模写されています。
北斎漫画の生き生きとしたスケッチは西洋の人物画に新たな表現をもたらしたと評されており、西洋の芸術家たちは競って北斎の造形から学ぼうとしたのです。
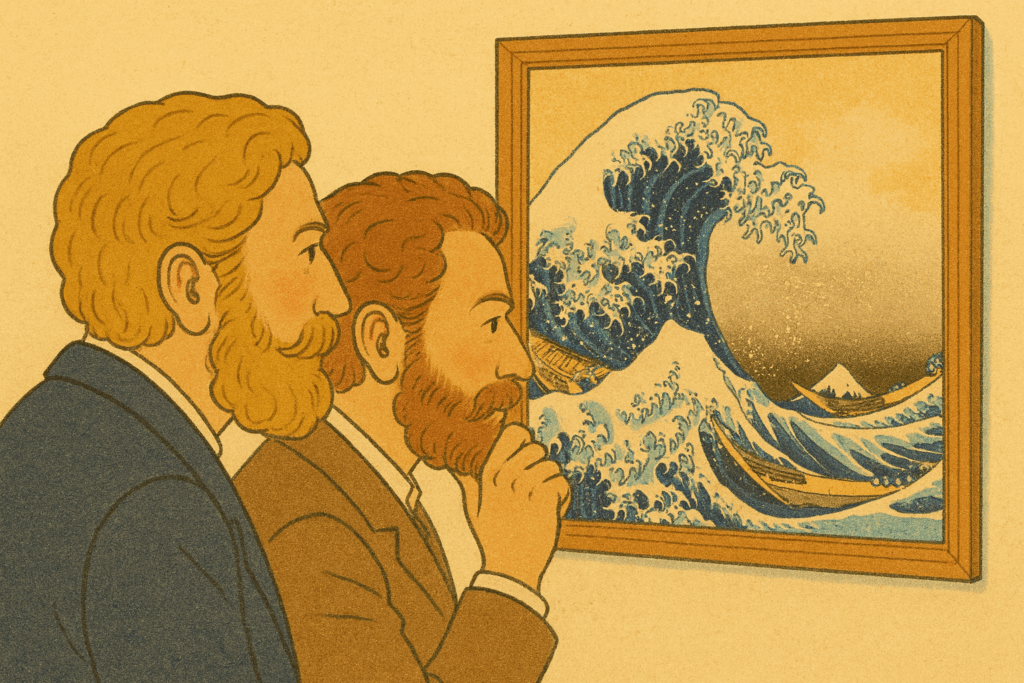
モネと印象派への影響
日本美術の熱烈な愛好家であったクロード・モネ(1840–1926)は、自宅の庭に日本風の太鼓橋を架け、200点以上もの浮世絵版画を収集していました。
そのコレクションには北斎の錦絵や画集も含まれており、モネの作品には日本的発想を取り入れたと見られるものが複数存在します。
たとえば油彩《木の間越しの春》(1878年)では、目の前の木立の間から川と対岸の家々を覗き見る構図が描かれていますが、これは北斎の画集『富嶽百景』二編にある竹林越しに富士山を望む場面を想起させます。
当時の西洋絵画には見られなかったこの大胆な“すだれ効果”の遠近法に、印象派の画家たちは大きな刺激を受けました。
実際モネ自身、ノルウェー滞在中に描いた雪山の連作を「富士山を思いながら描いた」と記した手紙が残されており、北斎の富士山連作の着想がモネの制作に影響を与えたことがうかがえます。
モネの睡蓮の連作や日本風の庭園も含め、その作風には北斎をはじめとする浮世絵から得た色彩や構図上のヒントが息づいているのです。


ゴッホの熱狂とポスト印象派
オランダ出身の画家フィンセント・ファン・ゴッホ(1853–1890)は、浮世絵から大きな影響を受けたポスト印象派の代表例です。
彼はパリ滞在中の1886年頃、画商から入手した多数の浮世絵をアトリエの壁一面に貼り出し、その色使いや構図の研究に没頭しました。ゴッホの描線や色彩にも日本的な平坦さと原色の大胆な配色が取り入れられており、これらは浮世絵から学んだ要素だとされています。
事実、彼の作品《タンギー爺さんの肖像》(1887年)では背景に歌川英泉の花魁図や広重の富士山など6枚もの浮世絵が描き込まれており、ゴッホの日本美術への傾倒ぶりが如実に示されています。
またゴッホは歌川広重の名所絵《大はしあたけの夕立》や《亀戸梅屋舗》を油彩で模写し、その構図や色彩を自作に取り込みました。
彼自身「北斎の波を見ていると『この波は爪のようだ、舟はその爪に捕まっているのが感じられる』と叫びたくなる」と述べ、北斎のダイナミックな表現に深い感銘を受けていたことが窺えます。
その他の画家たちへの広がり
北斎の影響は、モネやゴッホ以外の多くの西洋画家にも及びました。
印象派のエドガー・ドガ(1834–1917)は多数の浮世絵を所蔵し、特に北斎の『北斎漫画』に描かれた日常の何気ない所作やポーズに注目したとされます。
実際ドガの踊り子たちを描いた作品には、画面の端で人物が大胆に切り取られる構図など浮世絵的な特徴が見られます。

女性画家メアリー・カサット(1844–1926)も浮世絵の技法に学び、母子を題材に日本風の平面的構図の版画作品を制作しました。
またポスト印象派のポール・ゴーガン(1848–1903)はゴッホと共に浮世絵に傾倒し、自身の静物画に愛らしい子犬を三方向から描き込むなど、日本的な発想を取り入れています。
西洋では当時、小動物や昆虫が独立した美術の主題となることは稀でしたが、北斎の描くトンボや子犬の絵はそうした“小さな命”を慈しむ表現として新鮮な驚きをもって受け止められました。
アール・ヌーヴォーから現代アートまで
19世紀末に欧米で興ったアール・ヌーヴォー(新藝術)様式にも、北斎をはじめ日本美術の影響が色濃く表れています。
前述のガレを中心とするナンシー派の芸術家たちは、日本の図案や自然観に学び、植物や動物を主題とした装飾的なガラス・家具作品を次々に生み出しました。
フランスの彫刻家カミーユ・クローデル(1864–1943)は代表作《波》(1897年)において北斎の「大波」を想起させる造形を試み、西洋絵画だけでなく彫刻の領域にも北斎の造形イメージが取り入れられています。
さらに音楽の分野では、作曲家クロード・ドビュッシー(1862–1918)が交響詩《海(La Mer)》(1905年)を作曲する際、初版楽譜の表紙に北斎「神奈川沖浪裏」の図版を用いたことが知られています。
直接の影響か定かではないものの、ドビュッシーが当時誰も見たことのなかった北斎の大胆で新しい海の表現に触発された可能性は十分に考えられるでしょう。
時を下った20世紀以降も、北斎の与えた衝撃は色褪せることがありません。
ポップアートの旗手アンディ・ウォーホルは1980年代に《The Great Wave(After Hokusai)》という版画作品を発表し、ロイ・リキテンスタインも代表作《溺れる女》(1963年)の背景に北斎の波の形を引用するなど、20世紀美術においても北斎作品へのオマージュが多数みられます。
現代の日本人アーティスト奈良美智(なら よしとも)をはじめ、世界の現代美術家たちも北斎の作品からインスピレーションを得たと語っており、北斎のイメージは今日でもグラフィックデザインやファッション、アニメーションなど様々な領域に引用されています。
おわりに:北斎がもたらしたもの
北斎が世界の画家たちに与えた衝撃は、一言でいえば“まったく新しい視覚の可能性”でした。
その大胆な構図やユニークな発想は、西洋の遠近法や写実表現の常識からかけ離れており、19世紀の芸術家たちにとって驚きと発見の連続だったのです。
例えば『冨嶽三十六景』で見せる近景と遠景の極端な遠近感、モチーフの思い切った省略や誇張、輪郭線を活かした平面的な色彩表現――いずれも当時の西洋美術には見られなかったものでした。
折しも西洋の美術界は古典や写実主義からの脱却を模索する時期に差し掛かっており、既存の概念を覆す自由奔放な北斎の図像はまさに求められていた刺激となりました。こうした北斎芸術との出会いが印象派やポスト印象派、象徴主義やアール・ヌーヴォーといった新しい美術運動の胎動を後押しし、西洋美術の表現領域を飛躍的に拡大させたのです。
日本が生んだ巨匠・葛飾北斎。その創造力から放たれた衝撃波は、時空を超えて今なお世界中のアーティストたちの心を揺さぶり続けています。
